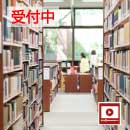教養・趣味をひろげる
社会保障を学びましょう・社会保障の基礎知識
|
教養・趣味をひろげる 社会保障を学びましょう・社会保障の基礎知識 |
講師 | 久保 知行 |
|---|---|---|
| 受講形態 | インターネット | |
| 受講料(税込) | 講座概要に掲載 | |
| 講義時間・回数 | 90分×8コマ |
| Tweet |
この講座の概要
//講座のご紹介
「社会保障を学びましょう」は、社会保障に興味を持ちつつ学習機会のない人向けに、社会保障とはどんなものかを説明します。「社会保障の基礎知識」は、上記で関心を持った人を対象に、社会保障制度の主要分野(少子化、公的年金、公的医療、介護)の内容を7回に分けて説明します。
※各回、説明60分+質疑応答(最大30分)を予定しています。
//申込期限等
【申 込 期 限】2026/2/25(水)※ライブ受講希望の場合は各開講日の3日前まで【入 金 期 限】2026/2/27(金)※ライブ受講希望の場合は各開講日の前日まで
【オンデマンド受講期間】2026/3/31(火)
//最小開講人数
10名※5月31日時点で最小開講人数に達しない場合は中止
//受講料
第1回(税込)一般・学生1,100円第2回~第8回 各回(税込)一般2,200円 / 学生1,100円
8回セット料金(上記第1回を受講後の申込でも適用)(税込)一般14,300円 / 学生7,700円
※学生は本学科目等履修生も含む
※学生は本学学生以外も含む
//支払い方法
銀行振込またはキャッシュレス決済(クレジットカード払い)//受講方法
インターネット受講のみ。ご都合に応じて以下の受講が可能です。参考:受講形態について(ページを移動します)・ライブ受講(決められた日時に受講。不明な点があればチャットを活用してその場で質問可能です ※受講生はカメラ・マイク不要です)
・オンデマンド受講(決められた期間内に何度でも受講可能です ※講師への質問はできません)
日程と内容について
| 日程 | 時間 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年 06月07日 |
10:00-11:30 | 〔社会保障を学びましょう〕社会保障とはどんなものかを説明 (社会保障制度の体系、公的扶助の概観、社会手当の概観) |
| 2 | 2025年 06月14日 |
10:00-11:30 | 〔社会保障の基礎知識 (少子高齢化)〕少子高齢化 の 状況と課題を 説明 (日本の人口動向、人口ピラミッドの推移、労働力・就業率の動向、 非正規雇用の問題、労働環境の変化) |
| 3 | 2025年 06月21日 |
10:00-11:30 | 〔社会保障の基礎知識(年金1)〕公的年金の基礎知識を説明 (公的年金の意義・役割と体系、公的年金の給付の種類、 保険料徴収方法と年金財政の状況、公的年金財政の将来見通し、 2020年年金改正法、2024年財政検証) |
| 4 | 2025年 06月28日 |
10:00-11:30 | 〔社会保障の基礎知識(年金2)〕公的年金の基礎知識を説明 (公的年金の意義・役割と体系、公的年金の給付の種類、 保険料徴収方法と年金財政の状況、公的年金財政の将来見通し、 2020年年金改正法、2024年財政検証) |
| 5 | 2025年 07月05日 |
10:00-11:30 | 〔社会保障の基礎知識(年金3)〕公的年金の基礎知識を説明 (公的年金の意義・役割と体系、公的年金の給付の種類、 保険料徴収方法と年金財政の状況、公的年金財政の将来見通し、 2020年年金改正法、2024年財政検証) |
| 6 | 2025年 07月12日 |
10:00-11:30 | 〔社会保障の基礎知識(医療1)〕医療保険の基礎知識を説明 (日本の医療制度の体系 、 医療保険の保険者別状況、 公的医療保険の給付内容、医療保険制度の沿革・国際比較) |
| 7 | 2025年 07月19日 |
10:00-11:30 | 〔社会保障の基礎知識(医療2)〕医療保険の基礎知識を説明 (日本の医療制度の体系 、 医療保険の保険者別状況、 公的医療保険の給付内容、医療保険制度の沿革・国際比較) |
| 8 | 2025年 07月26日 |
10:00-11:30 | 〔社会保障の基礎知識(介護)〕介護保険の基礎知識を説明 (日本の介護保険の体系 、 介護サービスの概要 、 介護保険制度を取り巻く状況、介護保険制度の沿革・海外制度 |
講師プロフィール
久保 知行
1952年生まれで、1974年に住友信託銀行(現・三井住友信託銀行)に入社し、勤続30年の後に、日産自動車に移り9年余勤務。この間、基本的に年金関連業務に従事した。住友信託銀行在職中に米国ハーバード大学客員研究員として1年間派遣された。
大学・大学院での講師経験としては、早稲田大学ビジネススクール、慶應大学大学院、横浜国立大学ビジネススクールで企業年金を教授し、日本大学では公的年金を含む年金全般を教授した。さらに、社会保障全般について、東京福祉大学で教授した後、日本国際学園大学(旧・筑波学院大学)に移って教授中である。
保有資格としては、年金の専門家である「年金数理人」(日本年金数理人会正会員)である。