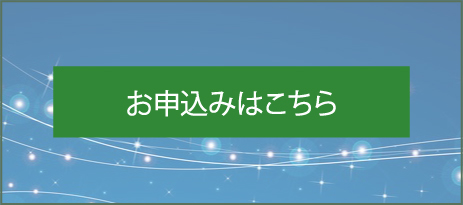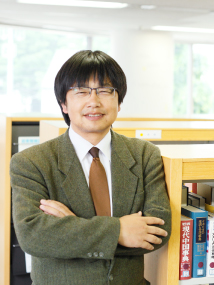教養・趣味をひろげる
【八洲学園大学国際高等学校 高大連携講座(2025)】体調をととのえる
|
教養・趣味をひろげる 【八洲学園大学国際高等学校 高大連携講座(2025)】体調をととのえる |
講師 | 鈴木 啓之 |
|---|---|---|
| 受講形態 | インターネット | |
| 受講料(税込) | 各回 (税込)1,650円 | |
| 講義時間・回数 | 90分×6コマ |
| Tweet |
この講座の概要
//講座のご紹介
「健康で文化的な生活」は理想ですが、現代においては日常生活の営みの中でさまざまな不調や体調不良に遭遇し、「生活の質(QOL)」の維持が難しくなっています。例えば慢性的なものとしては「睡眠不足や寝付けない」、「朝起きられない/朝食を胃が受け付けない」、「昼夜逆転など生活リズムの乱れ」、「慢性的あるいは周期的な頭痛や筋肉痛」などがあり、季節的なものとしては「冷え性やかじかみ」、「夏ばてや多汗」、「秋の夜更かしや春の朝起きの辛さ」などが挙げられます。そこで本講では、これら体の不調の背景にある生理的メカニズムを解きながら、日常生活のスタイルや行動の工夫による日常生活不調の予防と軽減策をいっしょに考えてゆきます。「体調をととのえる」講座の各回の話題は、(全体として連関しながらも)一話完結で相互に独立していますので、関心のある話題を選んで受講いただけます。
※「八洲学園大学国際高等学校の単位認定講座」ですが、どなたでも受講可能です。
※本講座は2024年に収録した講座です。
//申込期限等
【申 込 期 限】2026/2/25(水)【入 金 期 限】2026/2/27(金)
【オンデマンド受講期間】2026/3/31(火)
//支払い方法
銀行振込またはキャッシュレス決済(クレジットカード払い)//受講方法
インターネット受講(オンデマンド受講)のみ。参考:受講形態について(ページを移動します)※期間内であれば何度でも視聴可能です。
※受講生はカメラ・マイク不要です。
日程と内容について
| 日程 | 時間 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 90分 | 〔寝起きの不調と対処法〕「朝おきられない」「午前中は集中できない」「朝食が食べられない」「寝起きの顔のむくみがひどい」 といった不調は、生活の質を著しく下げ、遅刻や欠勤・欠席など社会的評価にもかかわります。 また、朝が弱い方は入浴中や立ち仕事での立ちくらみを起こしやすい傾向があります。 そこで、朝の不調のメカニズムを知ることで、日常生活の工夫や改善の方法を提案します。 |
|
| 2 | 90分 | 〔寝入りや睡眠の不調と対処法〕「寝つけない」「夜中に起きてしまう」ことは中高年に多い不調ですが、 近年は若年者でも夜更かしが顕著になってきました。 また、子育ての中で「子どもの寝かしつけに苦労する」ことも多いようです。 そこで、睡眠機構とその不調のメカニズムを知ることで、よい睡眠を得るための 日常生活習慣の工夫や改善の方法を提案します。 (例えば、「寝タバコ」や「寝酒」は、生理学的に寝つきを悪化させる習慣であることを説明します) |
|
| 3 | 90分 | 〔生活リズムの不調と対処法〕「月曜朝のつらさ」「睡眠時間の割に寝た気がしない」など、社会人や学生の休み明けの 不調が広がっています。また、不登校中学生の4割が「生活リズムの乱れ」を原因にあげ、 またその多くが不登校中の昼夜逆転生活を経験しています。 とりわけ未成年では生活リズムの乱れで学力や体力が低下することが分かっています。 そこで、忙しい現代における生活リズム維持の脆弱性と改善の工夫について提案します。 また、海外旅行における時差ぼけの機序と対処法についても、併せて紹介します。 |
|
| 4 | 90分 | 〔体温調節と発熱、冷え性・低体温症の予防〕ヒトが平熱を保つ仕組みを踏まえて、体調が悪くなると発熱する機序や合理的理由を学びます。 関連して発熱を逆手に取ってつけこむ感染症を紹介します。また、体温調節異常としての冷え性 や凍傷・子どもに多く見られる低体温症の機序と生活の中での予防法を提案します。 併せて、体温や血行からみた入浴の効用とリスク、温泉の泉質別の効能と禁忌についても紹介します。 |
|
| 5 | 90分 | 〔発汗と脱水、暑さへの対処法〕「多汗」を気にしている方もいれば、汗をかけずに熱中症になりやすい方もいます。 そこで、「運動」「暑さ」「緊張」「食事」など場面ごとの発汗の機序と役割を解説し、 脱水や無理な補水でおこる水中毒などの健康リスクと予防法を紹介します。 また、正装時などでの「汗をかかない方法」や運動時のパフォーマンスと汗の関係についても紹介します。 |
|
| 6 | 90分 | 〔頭痛・筋肉痛、慢性痛の予防と対処法〕慢性の頭痛や季節代わりの周期性の頭痛やひどい肩こり・背中の痛みは、生活や仕事に支障を きたしますし、周りの方に本人のつらさが分かりにくい不調です。 また、痛みがひどくなると吐き気・冷汗・顔面蒼白・呼吸困難といった自律神経症状にも 苦しめられることになります。 慢性痛は、生兵法はダメで初期のうちに医療機関にかかることが重要ですが、 本講では、痛みの機能と機序を理解し、日常生活における痛み発作の予防や予兆の察知、 痛みを助長する要注意食品について紹介します。 |
講師プロフィール
鈴木 啓之
経歴:八洲学園大学 教授、博士(医学)
専門分野、研究テーマ:ヒトの内的状態の他覚的客観評価、障害児生理心理学
【八洲学園大学 正規担当科目】
障害児の理解と支援/障害児の子育てとしつけ/医学一般/情報アクセシビリティとバリアフリーデザイン/不登校・ひきこもり特講
▼鈴木啓之 教授 詳細はこちら(八洲学園大学 大学サイト)
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_suzuki.php