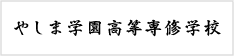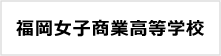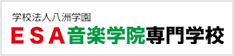授業紹介(1)地域と子どもの安全安心~地域安全マップをつくろう
2017/10/11
2017春期よりスタートした「地域と子どもの安全・安心~地域安全マップをつくろう」の授業と最終試験の課題を少しだけ紹介しようと思います。
本科目は、地域の住民(大人から子どもまで)が平穏な生活を送れるようにするための「安全」「安心」をどのように得ることが出来るかについて学んでいきます。
「安全」や「安心」は、受動的に得るものか、能動的に得るものなのでしょうか。
講義の中ではキーワードとして「領域性」「監視性」「抵抗性」をポイントに学んでいきます。
領域性とは、その場所に「入りやすく」「入りにくい」「逃げやすいか」
監視性とは、その場所が「見えやすいか」「見えにくいか」
抵抗性とは、危険にさらされたときに「抵抗して自己防衛をすることが出来るか」、具体的には護身術、防犯ブザー、防犯スプレー等が挙げられます。
また実際に福岡県某町、八洲学園大学周辺地域で調査をした写真などを活用してわかりやすく、面白く講義を行っています。
 時間別の様子と抵抗性、領域性、監視性を分析しています(学生の作品)
時間別の様子と抵抗性、領域性、監視性を分析しています(学生の作品)
 どのように対処すればよいのか具体的に示されています(学生の作品)
どのように対処すればよいのか具体的に示されています(学生の作品)
講義は、1単位科目ですので90分講義8回です。(秋期は、4学期よりスタートします)
最終試験は、試験方式でもレポート方式でもなく課題として受講生が住んでいる地域の半径250m程度の範囲の中で「地域安全マップ」を作成して頂きます。
2017年春期受講の学生の課題は、個性的なものであり、それぞれが学んだことを実践に活かしている。これからも様々な場面で知識を活かして誰もが安心して住める地域を作っていってくれるのではないかと思いました。
ここで2017年春期受講生の作品(課題)の一部をご紹介します。
8回講義に参加するだけでこのようなものを作れるようになります。
2017年秋期より開放授業として正規学生以外の一般の方も学べるようになりました。
詳細は、http://www.yashima.ac.jp/univ/extension/course/2017/09/--2.htmlまで
八洲学園大学パンフレット ※八洲学園大学の各種資料をダウンロード頂けます。
ご希望の資料はPDFでも閲覧可能です。
PDFファイルを閲覧するには、Adobe Acrobat Readerをインストールしてください。