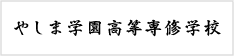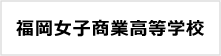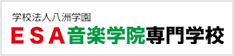温石(おんじゃく)
2011/03/18
ニュースで、震災の避難所の様子を知ることができます。辛い状況が続いています。灯油がなく、ストーブが使えないところが多いそうです。テレビでは、避難所の外でたき火をしている光景が見えました。でも、体の具合が悪くて横になっている方は、たき火のそばに行くこともできません。何とかしてあげたいです。が、遠く離れている身では、どうしてあげることもできません。室内で暖をとる方法は何か無いか、とずっと考えていました。そして、子どものときのことを思い出しました。
それは小学生の時の、冬の通学路のときのことでした。学校は、3キロの山道の彼方にありました。朝の通学路は寒くて、霜柱を踏みしめて学校に行きました。途中に、石切り場がありました。おじさんたちが、石を切り出している所です。そこにさしかかると、冬の間は、おじさんたちがたき火をしていました。石を切り出す仕事を始める前に、体を温めているのです。そのたき火に、当たらせてもらいました。その場面が上のイラストです。
子どもたちは、だれからともなく、にぎりこぶし大の小石をたき火の近くに転がしました。しばらくすると、小石が温かくなるのです。あまり熱くなりすぎないように、長い棒で小石の位置を調節しました。適温になったら再び小石を転がして、足元にもどします。そうしたら、その小石を手で直接さわらないで、帽子でくるみ、服の下のおなかのところに入れます。そうすると体が温かくなりました。50年も昔のことです。今でいう、「使い捨てカイロ」です。温かい石を入れた服の上からおなかを押さえて歩いていると、体中に温かさが回りました。
もし、可能であれば、これをされてみてはどうでしょうか。避難所の外でたき火をしているのであれば、その火の近くで小石を温め、それを長い棒で取り出して、布でくるみ、寝込んでいる方に届けてあげると、カイロになります。ただ、石が熱くなりすぎると、やけどをしてしまいます。だから、途中で、長い棒で石を取り出しては、温まり具合を確かめることが大切です。寒さを、何とか、乗り切りましょう。ご無事を祈っています。
尚、このように小石を温めて布にくるみ、体に当てる方法は、昔は病気の治療に使われ,その温めた石を温石(おんじゃく)といっていたそうです。
八洲学園大学パンフレット ※八洲学園大学の各種資料をダウンロード頂けます。
ご希望の資料はPDFでも閲覧可能です。
PDFファイルを閲覧するには、Adobe Acrobat Readerをインストールしてください。