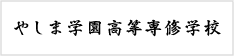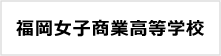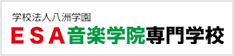平家の悲しみをたたえた関門海峡
2012/12/19

山口県下関市を訪ねた。目の前に関門海峡があった。向こうは九州の北九州市門司区。その距離600メートル。その間を潮流が川のように流れる。しかも、満潮干潮で日に4回、逆流がくりかえされる。
1185年春、平家の人たちはこの海の中に消えた。当初は潮の流れに乗って源氏との戦いを優位に進めたが、やがて、潮の流れは逆になった。義経の、櫓をこいでいる者を弓で射よ、というおきて破りの命令も加わった。平家の人々には、もう、なすすべはなかった。
平家物語はいう...
祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり
沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらわす
おごれる人も久しからず ただ春の夜の夢のごとし...
わたしたちは平家の人々に何を学べば良いのだろう。
考えてみると、戦いの悲惨さ、敗者の悲しさ、生きる場所を奪われる苦しみ、があげられる。それに、先を見ることの大切さがあげられよう。
見える流れに勢いがあると、それが逆流することへの関心が薄くなる。自分がその流れに乗っていれば、なおさらのこと。
平家に勝った義経も、そうである。戦いに勝った義経に、この後、自分が疎まれる存在になると、どうして考えられよう。しかし、あまりにも見事に勝ったので、もう、敵はいなくなった。自分の働きを示す場所はもうないのである。そうなると、勢いがある分、かえって目障りになった。
わたしたちも、そうである。
自分に勢いがあると、まわりが逆に流れ出すことに気づかない。
過ぎたるは及ばざるがごとし。
目先のことにとらわれず、
視野を大きくする努力を惜しまないことが大切だ。
流れは変わることを肝に命ずべし。
時代を超えての理である。
自分に勢いがあると、まわりが逆に流れ出すことに気づかない。
過ぎたるは及ばざるがごとし。
目先のことにとらわれず、
視野を大きくする努力を惜しまないことが大切だ。
流れは変わることを肝に命ずべし。
時代を超えての理である。
八洲学園大学パンフレット ※八洲学園大学の各種資料をダウンロード頂けます。
ご希望の資料はPDFでも閲覧可能です。
PDFファイルを閲覧するには、Adobe Acrobat Readerをインストールしてください。