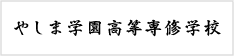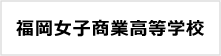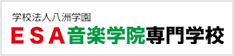現在を楽しむということ
2019/08/03

8月1日に、春学期の授業が終わりました。ホット、一息ついているところです。
最後の授業に、ゲーテの、次の言葉を引用しました。
「すばらしい人生を築きたいと思ったら、過ぎ去ったことは気にせず、腹を立てないようつとめ、いつも現在をたのしみ、とりわけ誰も憎まず、先のことは神様にまかせること。ゲーテ」(『ゲーテに学ぶ幸福術』木原武一・新潮選書より)
その中に、いつも現在を楽しみ…とありました。そうできるにはどうしたらよいかと思い返していて、あることを思い出しました。
あれは、まだ、春休みだった4月11日の未明のこと。前夜から原稿を書いていて、気がつくと夜明け間近になっていました。ラジオのスイッチを入れると、「ラジオ深夜便」のインタビュー。相手はイタリアを主な拠点に活動している安田侃(やすだかん)という彫刻家でした。話が大きかった。大理石の彫刻を公共の場所に展示しているが、千数百年たって地中からそれが出てきたとき、後世の人々がそれをどのように理解するかを楽しみにしていると。かつての紀元前後頃のギリシャ・ローマ時代の彫刻が、千数百年後にブドウ畑の中から掘り出され、それがミケランゼロなどに影響を与えて、ルネサンスを推進したように、と。なるほどなあ。自分のしていることが生かされるのは、今の世の中だけではないのですね。そう考えると気宇壮大な気持ちになります。そして、その安田さんの作品が、なんと横浜市の桜木町駅近くにあるというのです。桜木町は大学と同じ町内。さっそく出かけてみると、駅近くの日石横浜ビルの前の一角にそれはありました(写真)。
「天泉」という命名板が近くの地面に埋め込まれていました。天国の泉です。丸みをおびた大理石はさわると、とても心地よさを感じました。安田さんは、インタビューの中で、「この作品に登って遊んでいいですよ。人が一番上に登っても折れないように大理石の中に鉄骨を入れていますから。」と言っていました。これは体験型オブジェのような役割も果たしてくれるようです。見る人に、ここで遊びたいと思う気持ちや、居心地のよさをイマジネーションさせてくれます。泉とは、まさにそのような場です。千数百年後の人たちが、これを地中から見つけ出して遊ぶ姿を想像すると楽しいです。
そのように、だれかが、将来、自分のすることを楽しんでくれるだろうと思うことで、現在を楽しむことができます。先のことは神様に任せよう、と思う大らかさが、そのことを後押ししてくれるような気がします。
八洲学園大学パンフレット ※八洲学園大学の各種資料をダウンロード頂けます。
ご希望の資料はPDFでも閲覧可能です。
PDFファイルを閲覧するには、Adobe Acrobat Readerをインストールしてください。